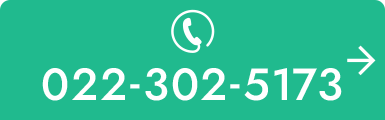親知らずに関するよくある質問
親知らずは必ず抜歯しなくてはいけませんか?
いいえ、まっすぐに生えていて虫歯や歯周病になっていない場合や、反対側の親知らずの歯としっかりと噛み合っている場合、抜歯する必要はありません。
一方、親知らずが斜めに生えている、歯ぐきに一部隠れている、歯ぐきの下に横向きに隠れている場合などは、周囲の歯ぐきの腫れを引き起こし、歯並びを悪くする原因となるので抜歯したほうが良いでしょう。
親知らずはお口の最も後ろに位置し,歯ブラシが難しくて磨き残しが多くなります。将来的に他の歯を失ってしまった場合、親知らずを移植するという方法もありますが、親知らずは虫歯や歯周病となるリスクが高いことから、抜歯しておくことをおすすめします。
親知らずがきれいに生える人はどれくらいいるのですか?
親知らずが問題なくきれいに生えている人は全体の30%程度とされています。
抜歯すべき親知らずを放置すると、歯ぐきが腫れて痛む(智歯周囲炎)、噛み合わせがおかしくなる、歯並びが変わってきたなどの症状が出てくるだけなので,早期の抜歯をおすすめします。
また、年齢が若いほど抜歯後の治りが早いので、できるだけ若いうち(10代後半から20代前半)に抜歯することをおすすめします。
親知らずを抜歯しないとどんな問題が起きますか?
虫歯や歯周病、嚢胞(のうほう)、歯並びの乱れ、噛み合う反対側の歯や隣のはの損傷などのトラブルを引き起こす可能性があります。
斜め向きや横向きに生えていたとしても、生えようとする力は一生涯続いていきます。そこでその力がしわよせとなって他の歯に働き,歯並びが悪くなるケースが多く認められます。
抜歯のタイミングはいつが良いですか?
早ければ早いほど良いです。歯ぐきが腫れて痛むときは、いったん炎症を抑えてから(抗生物質を服用してもらうなどの消炎治療を行ってから)、抜歯します。
抜歯すべき親知らずを放置すると、歯ぐきが腫れて痛む(智歯周囲炎)、噛み合わせがおかしくなる、歯並びが変わってきたなどの症状が出てくるだけなので,早期の抜歯をおすすめします。
また、年齢が若いほど抜歯後の治りが早いので、できるだけ若いうち(10代後半から20代前半)に抜歯することをおすすめします。
親知らずを抜歯すると腫れると聞きましたがなぜですか?
歯ぐきを切開して骨(顎骨)を削るからです。
あごの骨(顎骨)の中に埋まった親知らずを抜歯するにあたり、歯ぐきを切開して骨を削る必要があります。その侵襲に対する正常な体の反応として、おもに血液からの成分(滲出液、しんしゅつえき)が集まってくるため、抜歯した部位が膨張し、「腫れる」という結果が生まれます。
抜歯の侵襲程度にもよりますが、抜歯後10日間程度は腫れて,お口が開きづらくなると考えていただくとよいです。
広瀬通り歯科クリニックでは、とくに骨の中に埋まった埋伏歯の抜歯後に腫れることを少なくするために、あらかじめ患者さんの血液を採血させていただいて、その白血球成分を抽出して抜歯後の穴に埋めます。これにより、従来言われているような腫れや、お口が開けづらいという不快症状はほぼありません。
抜歯は痛いですか?
術中に痛みを感じることはありません。麻酔が切れた後に痛みが生じることがあります。術中に不安な方には静脈内鎮静法(ほぼ寝ている状態)の併用をお勧めします。
あごの骨に埋まっているかどうかなど、抜歯の程度にもよりますが、大きな手術ではなく、1時間程度で終わる小手術にあたるものですので、局所麻酔のみで行うのが一般的です。
手術後は、麻酔が切れた時に一時的に多少の痛みや腫れを感じることがありますが、処方した痛み止めを用いることによって解決されることがほとんどです。
広瀬通り歯科クリニックでは、手術に対する恐怖心が強い方に対して、静脈内鎮静法の併用をお勧めしています。全身麻酔とは違い、歯科麻酔専門医に委託して、よりリラックスした環境で安心して抜歯手術を受けていただけます。
抜歯にかかる時間はどのくらいですか?
30分から1時間程度です。
局所麻酔を行う時間を含めて、おおよそ30分から1時間程度で終了します。親知らずの抜歯は不安に感じることも多いですが、事前に知識を持っておくことで、よりスムーズに対応できます。もし不安がある場合は、歯科医院でしっかり相談することをおすすめします。
複数本の親知らずを一度に抜歯できますか?
できます。
局所麻酔の使用により術後2時間程度は頬っぺたなどの麻痺が続くため、術直後の生活を考慮すると通常は片側ずつ抜くことが多いです。
広瀬通り歯科クリニックでは、ご希望があれば静脈内鎮静法を併用して両側上下4本を一度に抜歯することも可能です。無料相談をぜひご利用ください。
親知らずの抜歯後、どのくらい腫れますか?
通常は術後2~3日目が腫れのピークで、1週間程度で落ち着きます。個人差はありますが、とくに下の親知らずの抜歯後は腫れやすい傾向にあります。
骨の中に埋まっている親知らずの抜歯では、歯ぐきを切開して骨(顎骨)を削るため、その侵襲に対する正常な体の反応として、おもに血液からの成分(滲出液、しんしゅつえき)が集まるため、抜歯した部位が膨張し、「腫れる」という結果になります。抜歯の侵襲程度にもよりますが、抜歯後10日間程度は腫れて,お口が開きづらくなることもあると考えていただくとよいです。
広瀬通り歯科クリニックでは、とくに骨の中に埋まった埋伏歯の抜歯後に腫れることを少なくするために、あらかじめ患者さんの血液を採血させていただいて、その白血球成分を抽出して抜歯後の穴に埋めます。これにより、従来言われているような腫れや、お口が開けづらいという不快症状はほぼありません。
抜歯後、どれくらいで食事ができますか?
軟らかい食事は当日から可能ですが、硬いものや刺激の強い食べ物は1週間ほど避けるのが理想的です。
手術当日は外科的な侵襲を受けたお口の粘膜が敏感となっていることから、粘膜を刺激する硬い食べ物や、酸っぱみや辛い物などは避けた方が良いでしょう。抜歯をしていない側で食べることも無難ですが、あごの筋肉をおかしくしてしまうので、できるだけ両側でゆっくりと食べてください。
抜歯後の出血はどれくらい続きますか?
抜歯後数時間はじわじわと出血することがありますが、通常はガーゼをしっかり噛めば止まります。出血が続く場合は歯科医院に相談してください。
通常は術後30分程度ガーゼをしっかりと噛んでいただくことで、ほぼ止血します。術後1日くらいはじわじわと軽度に出血することがあり、唾液を混じることで、出血が続くように感じますが、ご安心いただいて大丈夫と思います。
痛みを強く伴う場合は、歯科医院にご相談ください。
抜歯後、仕事や学校は休んだ方が良いですか?
軽度の抜歯であれば抜歯当日でも術後にお仕事は可能ですが、腫れや痛みが出ることがあるので、抜歯当日と翌日は休めるように調整すると安心です。
骨の中に埋まっている親知らずの抜歯では、歯ぐきを切開して骨(顎骨)を削るため、抜歯当日と翌日は身体を休めていただくと安心です。
抜歯後にお風呂や運動しても大丈夫ですか?
抜歯当日は血行が良くなると出血しやすくなるため、長風呂や激しい運動は控えてください。軽いシャワー程度なら問題ありません。
運動やお風呂、飲酒などの血行が良くなる行動は、手術部位の出血を促し、痛みを伴うこともあり得ます。抜歯当日は、ゆっくりとお過ごしください。
抜歯後にお薬は飲まないといけませんか?
痛み止めや抗生物質を処方されることが多いです。抗生物質(抗菌薬)は感染予防のため、指示通りに服用しましょう。
近年のガイドラインでは術後の抗生物質(抗菌薬)の投与は推奨されておらず、下あごの骨の中に埋まっている親知らずの抜歯に関してのみ、術前の投与が推奨されています。したがって、術前に抗生物質(抗菌薬)を飲むように指示されていることが多く、術後に飲むことは少なくなっていることでしょう。
痛み止めは、痛くなった時、あるいは痛くなりそうと感じたら飲むだけで結構です。
抜歯後、口を開けにくくなることはありませんか?
口を開けにくくなることがあります。
とくに下あごの親知らずを抜いた後は、顎の筋肉が炎症を起こし、一時的に口が開きにくくなることがあります。通常は1週間ほどで改善します。
広瀬通り歯科クリニックでは、とくに骨の中に埋まった埋伏歯の抜歯後に腫れることを少なくするために、あらかじめ患者さんの血液を採血させていただいて、その白血球成分を抽出して抜歯後の穴に埋めます。これにより、従来言われているような腫れや、お口が開けづらいという不快症状はほぼありません。無料相談をぜひご利用ください。
抜歯後,いつから歯磨きをしても良いですか?
抜歯当日は傷口を避けて全体を軽く磨く程度にしましょう。翌日からは優しく歯磨きできますが、傷口に直接触れないように注意してください。
歯ブラシ自体が刺激となって出血を促してしまうことがあるので、抜歯翌日以後も注意して歯磨きしてください。
下の親知らずの抜歯後にあごに麻痺が出たとの記事を読んだことがあるのですが大丈夫ですか?
術前の精密検査と診断によってリスクを回避します。
あごや唇、頬に麻痺が起きてしまうのは、下あごの下歯槽神経を傷つけてしまった場合が多いです。そこで、このような偶発症を防ぐために術前検査、とくにCT画像検査を行なって、下歯槽神経を傷つけないように抜歯する施術方法を考えて手術を行います。
場合によっては、下歯槽神経に近い根のところを一旦残して、2回に分けて抜歯することもあります。
妊娠中や授乳中でも親知らずの抜歯はできますか?
妊娠中は安定期(16~28週)であれば抜歯が可能ですが、医師や歯科医との相談が必要です。授乳中は局所麻酔や投与するお薬の影響を考慮しながら処置を行います。
基本的に妊婦さんや授乳期の方にはお薬を投与したくなく、侵襲は回避したいため、とくに骨の中に埋まっている親知らずの抜歯は避けたいです。
妊娠前に抜歯してしまうことを強くお勧めします。
親知らずの抜歯は医療費控除の対象になりますか?
医療費控除の対象となります。
医療費控除とは、1年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで税金の一部が還付される制度です。治療費以外にも、通院のための交通費なども対象となるので、治療費などの領収書は失くさずに保管しておいてください。
親知らずの抜歯は手術給付金の対象となりますか?
通常の抜歯手術は給付金支払いの対象とはなりませんが、親知らずが埋伏(骨の中に埋まっている)しており、骨(顎骨)におよぶ手術は支払いの対象となることがあります。
詳しくはご契約中の共済組合などにお問合せください。